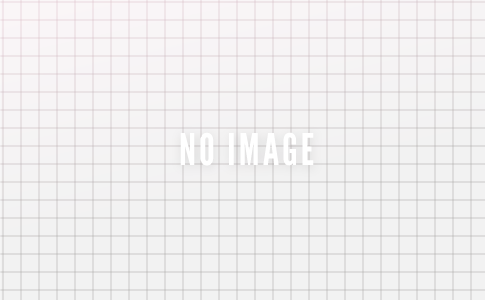おはようございます。ゴールドエッセンスの気ままなブログへようこそ。管理人のMOUです。
唐突ですが、管理人MOUは、心理学、スピリチュアルについて学んでいます。
具体的にどんなことを学んでいるのかというと、、
・大学院で心身相関について学ぶ
・SHIEN学
・アクセスバーズ
・アクセスフェイスリフト
・ヒーリング(MCIヒーリング)
・ゴッドクリーナー(購入した)
項目としてはこんなところです。ほかに、心理学の本を読んだりしています。
このうち、今日はSHIEN学についてお話しようと思います。
SHIEN学は、「支援学」と漢字では書かず、あえて「SHIEN学」としています。
創始者は舘岡康雄先生です。お会いしてお話したことが何度かありますが、とても気さくな話しやすい先生です。そんな、SHIEN学についてみていきましょう
SHIENとは「してあげる」ことではない?──「SHIEN」と聞いて、どんなイメージがありますか?
多くの人が、「支援」と聞いて思い浮かべるのは、
- 助けてあげること
- 困っている人をサポートすること
- 自立していない人を支えること
といったものなのではないでしょうか?
でも、舘岡先生のSHIEN学は、少し違っています。
「支援とは、本当に『してあげる』ものなのか?」
「その“支援”は、相手の力を引き出しているのか?」
「むしろ、相手の可能性を奪ってはいないか?」
この問いにドキッとした方、きっと少なくないはずです。
SHIEN学とは?──「関係性」に注目する学び
舘岡康雄先生が提唱するSHIEN学は、支援を「何かをする行為」ではなく、「人と人との関係性」として捉える学びです。
従来の支援は、
- 助ける人(支援者)
- 助けられる人(被支援者)
という上下の関係に陥りがちでした。
しかしSHIEN学では、支援とはそうした固定された関係ではなく、「共に在ること」「共に考えること」「共に学ぶこと」だと考えます。
「してあげる」支援の落とし穴
例えば、誰かに親切にしたとき、心のどこかで「良いことをしてあげた」と思うこと、ありませんか?
でもその「してあげる」という意識が強すぎると、
- 相手の自己決定の力を奪ってしまう
- 相手が「依存」する構造をつくってしまう
- 自分は「支援する側」に固定され、成長の機会を逃す
といった、支援の本来の目的からズレた関係を生んでしまいます。
SHIEN学が目指す支援のかたち
SHIEN学では、こんな支援のあり方を大切にしています:
- 上下ではなく横の関係性:フラットな対話から始まる支援
- 行為ではなく関係の質に注目:「何をしたか」より「どう関わったか」
- 支援は“する側”も“される側”も変化するプロセス:支援は学びであり、自己変容の場でもある
このように、支援は一方通行の「援助」ではなく、
“共に生きる”ことを選ぶ行為へと変わります。
教育・福祉・地域づくりへの応用
舘岡さんのSHIEN学は、理論だけではありません。
学校、地域、福祉の現場で、実際に多くの人がSHIEN的な関わりを実践しています。
たとえば:
- 教室で、教師が生徒に「教える」ではなく「一緒に学ぶ」姿勢を持つ
- 地域で、高齢者が支援を「受ける側」ではなく、「知恵を活かす側」になる
- 福祉の現場で、支援者が「何が正しいか」を決めるのではなく、「どうありたいか」を一緒に考える
こうした事例からもわかるように、SHIEN学は「支援」だけでなく、人と人の関係性全体を変える可能性を秘めています。
SHIEN学が私たちに教えてくれること
最後に、舘岡先生の言葉を借りて、この学びの本質をまとめてみます。
支援とは、行為ではなく関係である。
支援とは、相手の中にすでにある力を信じ、引き出すこと。
支援とは、共に変わり続けるプロセスである。
この視点に立つと、「誰かを支える」ことは、同時に「自分自身が支えられる」ことでもあると気づきます。してもらう、してあげる、関係とも言えます。また「利他的」と捉えることもできると思います。
なかなか捉えにくい概念かもしれませんが、管理人MOUはこの学びに出会ったことで、自分が人として一歩成長したなーと感じています。
ご興味がある方は軽ーい気持ちで一旦学びの一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
本日も最後までお読みくださってありがとうございました。
今日という一日が皆様にとって素敵な一日となりますように!
アロハ!!